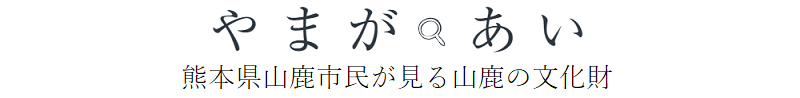大宮神社の神事である「献幣の儀」と「奉納灯籠」は行われます。
今年の「奉納灯籠」は自動車で運ばれてきますので「昨年までのような風情は感じられないかもしれない」と話されていました。
奉納された山鹿灯籠は、後日、灯籠殿で公開されます。毎年行われてきた奉納灯籠が当たる「おみくじ」は行われません。
毎年8月15日16日に開催されている山鹿灯籠まつり。
女性たちが頭に金灯籠(かなとうろう)をのせて踊る千人灯籠おどりや、まちなかの山鹿灯籠踊り、花火大会が有名で多くの方々が訪れられます。
2種類の山鹿灯籠「奉納灯籠」「金灯籠」

山鹿灯籠というのは御存知の通り、紙でできた工芸品です。
種類は大きく分けると、女性たちが頭に乗せる「金灯籠(かなとうろう)」と、宮造りなど、建物を作る「奉納灯籠」になります。工芸品としての山鹿灯籠は平成25年に国の伝統的工芸品に指定されました。

奉納灯籠は、「宮造り」「座敷造り」などの建物や「古式台灯」などが作られます。
作るのは、長く修行を積んだ山鹿灯籠の灯籠師です。
山鹿灯籠の制作は、山鹿市中心部付近の各町内から山鹿灯籠を専門に作る灯籠師に依頼されます。材料は紙と糊、金箔などだけを用いて作られ、完成した奉納灯籠は山鹿灯籠まつりの数日前より、16日のまつりが終わる頃まで各町内で大切に展示されます。
そして、8月16日夜、展示されていた奉納灯籠は、地区の人々の手により大宮神社へ向けて「ハーイ、トウロウ」の掛け声とともに動き出します。これを「上り灯籠」と呼び、山鹿灯籠まつりの重要な行事である、奉納灯籠のはじまりです。
大宮神社の神事「奉納灯籠」

山鹿灯籠まつりというと、女性たちがヨヘホ節に合わせて踊る山鹿灯籠踊りが有名です。その踊りは優美であり、わたしたちの目を引きつけてくれ、とても魅力的です。
ですので、どうしてもメディアや市の観光としては、魅力的な方を多くの方の目にとまるように広告をされます。しかし…
地元の方々からよく聞いていたのは、「ほんとうの山鹿灯籠まつりは、昭和に始まった灯籠踊りではなくて、奉納灯籠だもんね」という言葉です。
山鹿灯籠まつりは、市内にある大宮神社の例大祭で、神社での神事が行われるのですが、この神事というのが山鹿灯籠のうち奉納灯籠が大宮神社に奉納される「奉納灯籠」になります。
奉納灯籠とは、作られた山鹿灯籠そのものであり、また、神事の名称となっています。
山鹿灯籠は 夜明かしまつり

山鹿灯籠音頭の一節に
「山鹿灯籠は 夜明かしまつり ヨヘホ ヨヘホ」
という箇所があります。
以前の山鹿灯籠まつり、奉納灯籠は、まさに夜明かし祭りでした。
祭りの終盤、8月16日のよる11時頃になると、「ハーイ、トウロウ」の掛け声が聞こえてきます。山鹿灯籠師がその手でひとつひとつ紙で作り、市内各所に展示された宮造りや座敷造りの「奉納灯籠」を担いだ地区の人々が、「ハーイトウロウ」の掛け声を出しながら、大宮神社に集まってくるのです。
17日午前0時直前、大宮神社付近では、鳥居の前から坂の下まで、各地から集った奉納灯籠の長い列ができます。列をなす人々は、最後は鳥居をくぐり大宮神社の急な石段を奉納灯籠を担いでのぼり、拝殿の前で宮司さんよりお祓いの神事を受け、山鹿灯籠「奉納灯籠」が大宮神社に奉納されます。
その後、お祓いを受けた奉納灯籠は神殿の裏の広場に展示され、地区ごとに奉納灯籠の前で関係者にお神酒が披露されます。
ずっと以前は、このあと奉納灯籠を町内に持ち帰る「下がり灯籠」が行われていました。現在は下がり灯籠は行われておらず、大宮神社境内にある灯籠殿に収めらて1年間展示されることとなります。
見やすくなった奉納灯籠

以前、奉納灯籠は17日夜0時からでしたが、人々の仕事の事情などにより、8月16日の夜10時から開催されるようになりました。
まちなかでヨヘホ節に合わせて踊る女性の列を見ていると、どこからか「ハーイ トウロウ」の声が聞こえてくるのは、時間が早くなったからです。
祭り行事の時刻が変更になったものの、その分だけ、奉納灯籠を知らなかった方々にも大宮神社例大祭、山鹿灯籠まつりの神事、奉納灯籠を運ぶ山鹿の人々の姿を見ることができるようになったのではないかと思います。
お時間に余裕がある方、とくに山鹿市内にお住まいの方は、ぜひ一度は大宮神社での神事「奉納灯籠」も見られてくださいね。
関連文化財
指定文化財

関連記事