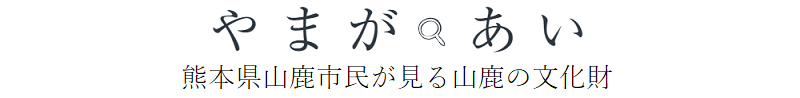旧山鹿郡三十三観音(きゅうやまがぐんさんじゅうさんかんのん)
山鹿市には旧山鹿郡のうち、旧山鹿市、旧鹿本町、旧菊鹿町にある三十三の観音様を巡る、旧山鹿郡三十三観音があります。
各札所のガイドは、姉妹サイト、旧山鹿郡三十三観音 札所巡礼ガイドに書いています。
旧山鹿郡三十三観音巡礼は、1番札所の豊前街道沿いにある金剛乗寺内から、菊鹿町の千手観音で有名な相良寺(相良観音)まで、約70kmですので自転車でも充分に回れる行程です。
以前に私が自転車で回ったときにルート沿いで見た、道中にある山鹿の名所などを書いていきます。
第一番札所から第十番札所までの見どころ
1 紫雲寺 九日町
豊前街道九日町にある金剛乗寺内です。
2 川辺寺 南島
山鹿惣門跡や南嶋菅原神社の御神木を見つつ、国道3号線を渡った場所です。
3 子安寺 志々岐
すぐ近くには閻魔堂があります。
4 観福寺 小原
岩原周辺の横穴群の近くを通っていきます。観福寺は林の中にありますので、ヤブ蚊に注意です。
5 智徳寺 鍋田
観福寺の川向うにあるため小原からグルっと回って行かなくてはいけません。少し坂を登った先にありました。
6 宝性寺 鍋田
装飾古墳である鍋田横穴を横目に坂を登ると住宅地中にあります。
7 集林寺 石
チブサン古墳に少し立ち寄り、川の方に下ると7番札所が見えてきます
8 東向寺 城
馬塚古墳の円墳の墳丘を右側に見つつ進んでいくと8番札所です。
9 円通寺 城
8番札所から近いのですが、少し入り組んだ場所にあって、見つけたときに「あったー!」と声を上げてしまいました。
10 千福寺 城
集落の一番奥にあって、木々に囲まれたお堂です。
4番札所が林の中にあって、少しわかりにくいかなと感じましたが、どこか不思議な雰囲気が漂う場所でした。
鍋田付近には鍋田横穴群、代表的な装飾古墳であるチブサン古墳など、見どころがたくさんあります。

第十一番札所から第十九番札所までの見どころ
11 安養寺 津留
山沿いを三岳小学校方面に行った先にあります。最近はコンビニができたので一休みできますね。
12 野辺田観音堂(柳井寺) 小坂
ここには六地蔵幢が2基あったり、磨崖仏があったりと見どころが沢山あります。
13 法華寺 寺島
岩野川沿いを下ると左側に法華寺の集落が見えてきます。奥の急坂を登りきったところに法華寺のお堂があって、境内には石塔が沢山あります。
14 志徳寺 寺島
もしかしたら、ここが一番わかりにくいかもしれません。私が行ったときにはいくつかルートが有り、困難な溜池沿いから向かいました。参拝したあとに楽なルートを見つけてしまいまったのですが良い思い出です。溜池沿いルートは現在は通れるか不明です。
15 周法寺 杉
オムロン入口の反対側、3号線を少し入った畑の隣にあります
16 光明寺 上吉田
周法寺からカルチャースポーツセンターを通り吉田に向かうと、民家の菜園のとなり、敷地の角にお堂があります。どこもそうなのですが、道が細くて車を止める場所がなく、自転車で行って良かったと感じたことを思い出します。
17 観念寺 熊入町
せっかく吉田に行ったので久原に行きたいところですが、そこは20番。17番は熊入まで戻ることになります。住宅地の階段を登ると見えてくるのが観念寺。石造が沢山並んでいました。
18 長源寺観音堂 山鹿
ここを2番札所にしてほしかったと思いつつたどり着きました。参道前の六地蔵幢が目印になります。すぐ近くにはさくら湯前の薬師堂、そこに特徴的な六地蔵があったり、豊前街道沿いには樹齢400年超えの湯の端のエノキがあります。エノキは1番から2番に行く時以来の再会ですね。
19 雲閑寺 中村
雲閑時は山鹿温泉の発展に貢献した宇野親治のお墓があります。雲閑寺の境内、沢山の石仏があって見どころ満載です。また、近くには中の六地蔵幢もあります。
第十三番札所法華寺は2018年頃に建て替えられて新しくなったと聞きました。直前の急坂を思いっきり登りましょう。
第二十番札所から第二十九番札所までの見どころ
20 蓮生寺 久原
再び久原に戻ります。道中には大宮神社があり、馬頭観音のお堂があったりと見どころがありますね。自転車だと気軽に立ち寄れておすすめです。蓮生寺は小さなお堂ですがきれいに保たれています。近くには一ツ目神社と遊水地があって、ほんとに運がいいと珍しいトンボがいたりします。
21 京通寺 久原
近所の人にたくさん聞いてやっとたどり着いたことを思い出します。ここを出ると次は蒲生ですが、三玉郵便局の先のクランク部分に綺麗な六地蔵幢を見ることができますのでぜひ。
22 凡導寺 蒲生
不動岩のお膝元と行ってもいい場所にあります。ずっと以前にドラマのロケがあったらしく、記念の看板がありました。
23 岩隣寺 蒲生
凡道寺を出たあと2つの六地蔵をみつつ、蒲生の住宅地に向かうと岩隣寺があります。ここはなんといっても仁王像が特徴的で見入ってしまいます。
24 実西寺 鹿本町御宇田
実西寺は民家が立ち並ぶ場所にあってとても小さなお堂になります。平安末頃、御宇田地区を治めていた御宇田氏によって建てられた御宇田五山の1つ、実西寺跡です。近くには山鹿でも珍しい、お地蔵さんが線刻で描かれた御宇田の六地蔵幢があります。
25 中正寺 鹿本町御宇田
24番から御宇田神宮方面に行くと左手奥にお堂が見えます。住宅敷地への入り口部分なので結構気を使ってしまいます。
26 坂東寺 鹿本町来民
来民の商店街を抜ける前の場所にあります。もし余裕があるのでしたら、肥後銀行来民支店の近く(来民うちわの栗川商店の近く)にある公園に天然記念物である樹齢350年の「来民のイチョウ」があります。幹周りが大きくて迫力があるのでぜひ見ていかれてください。おすすめです。
27 円福寺 鹿本町高橋
26番からは鹿本体育館方面ルートがおすすめです。いつも綺麗な六地蔵幢や高橋八幡宮の石工仁平作の猿田彦やイチイガシの夜泣貝、その先には高橋の六地蔵幢が見れます。円福寺は民家の敷地内と思えるような場所です。駐車などでご迷惑をかけないように注意されてください。
28 平原寺 鹿本町津袋
円福寺から菊鹿方面に行くと五社宮の鳥居があり、そこをくぐった先に平原寺のお堂があります。その先には菊池氏が建てた五社宮神社と津袋古墳群の五社宮古墳への長い階段あります。余裕があれば見られてみてください。
29 光明寺 鹿本町庄
平原寺から少し戻り庄方面に行くのですが、途中左手に内田川沿いでは珍しい装飾古墳の五霊塚古墳があります。現在は保護のためにシートに囲われ中を見学できませんが、内部は美しい装飾があります。さらに、ルートからは外れますが菊鹿方面に行くと松尾神社や苔が綺麗な岩隈山の切り通しがあります。光明寺は建て替えられて綺麗なお堂です。
第三十番札所から第三十三番札所までの見どころ
30 玉泉寺 菊鹿町下内田
光明寺から内田川沿いを行くと日本遺産に登録された御宇田井手の扇形分水を見れますし、分水の近隣には平原塚古墳、朱塚古墳があります。これらの場所から、内田川の左側ルートを菊鹿方面に行ったところに玉泉寺があります。近くには、石工金七が造った川西の六地蔵や、現存する中で県内最古の川西の宝篋印塔があります。この辺りを治めていた内田氏が建てた宝篋印塔です。近くの丘には内田氏のお城もあったそうです。
31 長谷寺 菊鹿町長
内田川沿いの道を住宅のある方向へ長谷寺があります。お堂の前までたどり着く道はほんとに狭いので徒歩か自転車で行かれて下さい。
32 尋居寺 菊鹿町長
長谷寺からさらに菊鹿町の奥に進んでいき、栗の実保井育園がある反対側の内田川に架かる橋を渡ると、住宅地の三叉路の場所に尋居寺があります。
33 相良寺 菊鹿町相良
いよいよ最終、三十三番札書の相良観音です。尋居寺からここまでの道中では、ぜひ特別天然記念物のアイラトビカズラを見ていかれて下さい。
相良観音では千手観音を拝観したり、参道で売っている栗まんじゅうを食べましょう。
旧山鹿郡三十三観音を巡るルート付近には、様々な見どころがありますので、ぜひ巡って様々な山鹿を見られてください。
旧山鹿郡三十三観音 一覧
旧山鹿郡三十三観音 一覧表です
| 札所番号 | 名称 | 場所 |
| 1 | 紫雲寺 | 九日町 |
| 2 | 川辺寺 | 南島 |
| 3 | 子安寺 | 志々岐 |
| 4 | 観福寺 | 小原 |
| 5 | 智徳寺 | 鍋田 |
| 6 | 宝性寺 | 鍋田 |
| 7 | 集林寺 | 石 |
| 8 | 東向寺 | 城 |
| 9 | 円通寺 | 城 |
| 10 | 千福寺 | 城 |
| 11 | 安養寺 | 津留 |
| 12 | 柳井寺 (野辺田観音堂) | 小坂 |
| 13 | 法華寺 | 寺島 |
| 14 | 志徳寺 | 寺島 |
| 15 | 周法寺 | 杉 |
| 16 | 光明寺 | 上吉田 |
| 17 | 観念寺 | 熊入 |
| 18 | 長源寺 | 山鹿 |
| 19 | 雲閑寺 | 中 |
| 20 | 蓮生寺 | 久原 |
| 21 | 京通寺 | 久原 |
| 22 | 凡導寺 | 蒲生 |
| 23 | 岩隣寺 | 蒲生 |
| 24 | 実西寺 | 鹿本町御宇田 |
| 25 | 中正寺 | 鹿本町御宇田 |
| 26 | 坂東寺 | 鹿本町来民 |
| 27 | 円福寺 | 鹿本町高橋 |
| 28 | 平原寺 | 鹿本町津袋 |
| 29 | 光明寺 | 鹿本町庄 |
| 30 | 玉泉寺 | 菊鹿町下内田 |
| 31 | 長谷寺 | 菊鹿町長 |
| 32 | 尋居寺 | 菊鹿町長 |
| 33 | 相良寺 | 菊鹿町相良 |
山鹿に住んでいる方であれば、大体の距離感覚がわかると思います。
旧山鹿ではグルっと回っていきますが、鹿本町、菊鹿町になるとほぼ一直線にあります。
今は、Google Mapなどがあり、スマホ片手にルートが明確にわかるのですが、最初に設定された頃は、整備されていない道も多くさぞ大変だっただろうと想像できます。現在でも、第十四番札所の志徳寺は道を知らなければ行きにくい場所にあったりします。
地名の読み方
久原(くばる) 蒲生(かも) 来民(くたみ) 御宇田(みうた) 鹿本(かもと)