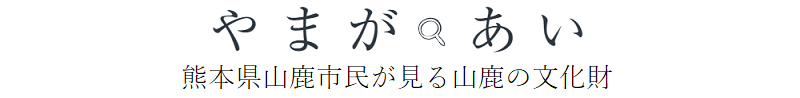2020年6月19日に鹿央町にある六地蔵をまわってきました。今回行った5箇所はすべて山鹿市の指定文化財になっていました。なお、指定されたのは2005年以前の鹿央町の時代です。
広の六地蔵
 上広の六地蔵 2020年6月19日
上広の六地蔵 2020年6月19日山鹿市の指定文化財に指定されている上広の六地蔵幢。基台から宝珠までほぼ欠けがない綺麗な状態です。
姫井の六地蔵
 姫井の六地蔵 2020年6月19日
姫井の六地蔵 2020年6月19日三叉路に建つ六地蔵です。こちらの特徴は…と考える前に、あるはずの物がないと気づきました。姫井の六地蔵幢はとても風化が激しく、龕部に彫ってあるはずの地蔵菩薩がすべて失われています。
傘や中台も欠けが大きいのですが、宝珠はしっかりと傘の上に載っています。「宝珠が残ったのは奇跡では?」といいたい気分になりました。しっかりと立ち、この地区を守り続けてこられた六地蔵さんなのですね。
見た感じで相当古いものと思ったのですが、市の説明文によると江戸時代に作られたもののようです。
霜野の六地蔵
 霜野の六地蔵 2020年6月19日
霜野の六地蔵 2020年6月19日霜野大日堂の境内にある六地蔵幢です。
1826年に再建されたということですので、それ以前に造られたものです。傘が少しいびつな形をしていることがわかります。『山鹿市の指定文化財』によると、龕部より上は室町期の様式を残しているとのことです。
宝珠はきちんと宝珠の形をして、中台や幢身、二重になった基礎はしっかりと六角形をしているのに傘だけがこのような形なのです。
龕部は写真の左側の下部が大きく欠けていますが、他の面では彫られたお地蔵さんはしっかりと残っていました。
宮前の六地蔵
 宮前の六地蔵 2020年6月19日
宮前の六地蔵 2020年6月19日1822年に建造された六地蔵幢です。
名前の通り、すぐ近くの霜野日吉宮の前に元はあったのですが、康平寺にいらした地元の方に聞いてみたところ、2016年に起こった熊本地震を受け、民家の方に倒れる危険性があるために現在の霜野公民館の方に移されたそうです。(最初は神社の前とは別の場所に建てられたのだと思われますが、不明です。)
基台は地中だと思われます。幢身・中台・龕部・傘・宝珠まで全てがとても綺麗です。
堂米野の六地蔵

堂米野の六地蔵幢は山鹿市内でも珍しい、線刻によるお地蔵さんになります。

山鹿でよく見かけるのは、半肉彫という体の前の部分を盛り上げるように彫られたものなのですが、堂米野の六地蔵幢の龕部(がんぶ-お地蔵さんが彫られる部分)には写真のように石を線で彫って地蔵菩薩を現されています。線刻で描かれた六地蔵幢は、市内最古の小坂の六地蔵、鹿本の御宇田の六地蔵、そして堂米野だけしか私は見ていません(※2020年6月19日現在※小坂のは肉眼では分かりづらい状態)
この日、行ったときには、タイトルを「森に飲み込まれる六地蔵幢」としたいくらいでしたが、実は、Google Mapのストリートビューでは木に覆われていない堂米野の六地蔵幢を見ることができます。
なんだか、スッキリしていらっしゃいますね。