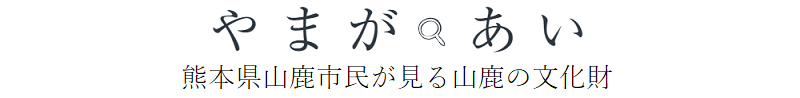岩隈山の切り通し、苔がきれいですね。棚になっている部分には石仏がたくさん置いてあります。
実はここ、子どもたちにとっては恐怖の通り道だったのです。

子供の頃から知っている切通し、Google Mapを見ていると、何やら史跡のマークがあります。場所は分かるけど、まさかここが史跡とされているとは、驚きでした。

全体が苔に覆われ、石仏が並び、なにやら塞がれた空洞があり、上部には竹が生い茂り、昼間でも薄暗くてジメジメしている場所。
中学生・高校生、もしかしたら小学生も。
夕方の帰り、ここを通る学生さんもいたでしょう。昭和の時代であればなおさら、徒歩で通られたと思います。子どもたちにとって日常である通学路、「できるなら避けたい場所」であったことは確実です。
地元の人達にとって、便利な道であるのですが、大人になった今でも夜に車でも通りたいとは思えない場所です。

それが、いま、「パワーを感じる」「苔がきれい」という言葉とともに来られる方がいるとは。
観光地というのはそういうものでしょうね。
ただ、ここは観光地ではなく、生活のための道であるということは忘れてはいけません。
この辺りの昭和中期の地図を見ると、現在は舗装されている、鹿本方面から松尾神社横を通り、山をぐるっと回り込み体育館がある場所への道路がみあたらず、この切り通しを通らなければかなり遠回りをしなければいけなかった可能性があります。
切り通しがいつ作られたかは分かりませんが、この辺りを治めていた人が命じて作らせたのかもしれません。切り通しができて、本当に便利になったのだと思います。
広報やまが(2011年9月号)に少しだけ岩隈山の切り通しのことが掲載されています。
昭和の初め頃までは通行中に大怪我をする人もいたことから、更に山を削り、現在の状態に近づいたようです。今は更に改良されて側面がコンクリートで覆われて以前よりも安全に通行できるようになっていますね(大雨大風時除く)。
今の平面に近い状態にするための工事では大量の土砂が出たということですから、西方寺あたりから切り通しを抜けた龍徳まで短い区間ですが、丘を登るような斜面だったと想像できます。

切通しの入り口に記念碑があります。
この記念碑は切通しとは直接関係はないのですが、そこに並べられている石仏について書かれているものです。
この地区に明治大正の頃に住んでいた方が、厚い信仰心から石仏を八十八体彫り、ここに祀られたということです。
もしかしたら、その時に作られた石仏が切通にも並べられたものではないかと、近くにある説明文に書かれています。
これからも長く、この道は地元の人によって使われると思います。
※強い風が吹いた直後は上から竹が落ちてくるので通ったらいけません。そもそも竹で塞がれて通れませんが…日頃もお気をつけて。
岩隈山の切り通しを、広い道の方から通り過ぎたところにはお寺があり、左折して少し行くと、1200年前に岩隈山に建てられた松尾神社があります。
松尾神社には面白い石造仁王像や石造カッパがありますので、興味がある方はお立ち寄りください。